株式会社設立手続・新会社法での会社設立
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 下記は株式会社設立手続の一例です。 およそ下記の流れで株式会社が設立となります。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■新会社法とは | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 「新会社法」とは、平成18年5月からスタートした新しい法律です。以前は、営利法人(株式会社、有限会社、合名会社、合資会社)を規制するいくつかの法律を総称して「会社法」と呼んでいました。今回の商法改正では、会社に関連する複数の法律を一つに総合して、新たに「会社法」という法律名で独立して法定されます。明治32年の商法成立以来の大改正ともいわれていて、中小企業に大きな影響がでてきています。 主な改正内容は下表のとおりです。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上記の表の中でも、会社設立に関して大きく変わったのは、下記の3点です。 ■ 有限会社が無くなった? 現在の有限会社は、株式会社に一本化されて統合されました。 新会社法施行後は、有限会社を新たに設立することはできなくなりました。 では、現在経営している有限会社はどうなるのか? 考えられるのは、2つの方法です。 1. 株式会社へ組織変更する。 ・ 有限会社から、株式譲渡制限会社への組織変更。 ・ 有限会社から株式譲渡制限のない株式会社への組織変更。 定款を変更後、登記することに よって、株式会社に組織変更することができます。 2.現存の有限会社として存続する。 特例有限会社として、既に経営している有限会社は存続できます。しかし、多くの有限会社は 株式会社に組織変更するものと思われ、有限会社という存在が珍しくなっていくことを考えると株式会社への組織変更を考えるのが良いと思われます。 ただ、情緒あふれる昔ながらの有限会社の旅館などは、有限会社の社名で歴史を感じられて くるので、あえて有限会社を残すケースもでてくるでしょう。 ■ 株式会社を設立しやすくなった! 今までは、有限会社での設立の場合は、300万円の資本金で、取締役一人でも設立できてい ました。株式会社は、資本金1000万円、取締役3名以上、監査役1名以上での設立とハードル が高かったのですが、新会社法施行後は、株式会社でも、取締役は1名で、資本金も1円 からの設立が可能となりました。 ■ 日本版LLC(合同会社)が新設された 日本版LLCとは、有限責任会社(Limited Liability Company)」の略称で、出資者である社員については有限責任となり、会社の内部関係については組合的規律が適用され、柔軟な内部組織を設計することができる組織です。以下のような特徴があります。 ・ 内部組織の取り決め 取締役・監査役といった内部組織のルールを自由に決められます。 ・利益配分(出資割合が低くても、貢献度の高い者には高配当を出す事も可能)を自由に設定できる特徴を持ちます。 この制度の本場は米国ですが、米国のLLCとの違いは、「パススルー税制(構成員課税)」 が日本版LLCには導入されていないということがいえます。 LLC(合同会社)設立手続はこちら(リンク) その他、上記3点以外にも多くの改正があります。その他の改正を下記に記載します。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.最低資本金規制が廃止 株式会社は1,000万円、有限会社は300万円の最低資本金が不要となり、最低資本金規制はなくなりました。 平成15年2月に施行された新事業創出促進法の特例によって、時限的に一定の条件のもとで、最低資本金規制を受けず1円でも株式会社・有限会社を作ることができました(いわゆる1円会社)が、この時限立法が廃止され、これによって設立された会社はそのまま存続できます。 2.類似商号・目的の規制は緩和 類似商号規制とは、同じ市町村において他人が登記した商号を同種の営業について登記することを禁止することです。この類似商号規制は廃止されました。 ただし、商標権等の兼ね合いがあるので、有名企業と同一名称となる場合等には十分注意が必要です。「不正目的の商号使用」の禁止も維持されるため、商号使用差止め請求も引き続き可能です。 類似商号規制の撤廃と同時に、類似の判断基準となっていた「会社の目的」についても記載基準が緩和されます。これまでは、会社設立時の「会社の目的」に係る語句の使用が厳格で審査に時間と手間がかかっていたことから、「会社の目的」について、包括的な記載が認められます。 3.発起設立の「払込金保管証明」が不要に 株式会社を設立する場合、法務局での設立登記に際して、株式会社に出資する金額が正しく払込取扱機関に払い込まれていることを示す「払込金保管証明」が必要でした。 しかし、法定手続きである「払込金保管証明」を行うべき銀行等の金融機関が、万一の場合の「証明責任」を恐れるあまり、既存の取引実績のない「新設会社」の「保管証明」を行わないことが多く、事実上、会社設立にとっての大きな障害となってきたのです。 新「会社法」では、発起設立の場合は払込金保管証明は不要で、銀行等での残高証明でよいことになります。これによって、設立手続きがより簡便になり、また設立日までその資金を使用できないといったこともなくなりました。 なお募集設立の場合には、払込金保管証明が必要となります。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■取締役、監査役等の機関設計が柔軟に | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1.取締役は1人でもよくなった 株式譲渡制限会社(多くの中小企業が該当します)は、従来義務付けられていた取締役会の設置が任意になります。取締役会を置かない場合は、取締役の人数は最低1名でもよいとされました。取締役会を置く場合は取締役は3名以上必要です。 任期についても従来は取締役2年、監査役4年でしたが、定款で定めれば、各々最長10年まで延ばせることになりました。 2.株主総会の重要性が高まる 従来、義務づけられていた取締役会の設置が任意になります。すべての株主総会で決議します。 各取締役への監督機能も株主総会が果たすなどその権限が強まります。そこで株主総会を開催しやすくするために次のような改正が行われています。 ①株主総会の招集通知は会日の1週間前(定款で短縮可能)までに通知すればよく、招集通知は書面等によらなくてもよくなりました。 ②開催場所も、「本店所在地またはその隣接地」という制限が廃止され、任意に決められることになりました。 ③株主には単独での議案提案権が認められました。 などといった、様々な改正がされました。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
当センターでは、新会社法にそくして、最適なスタイルの会社設立手続をいたします。
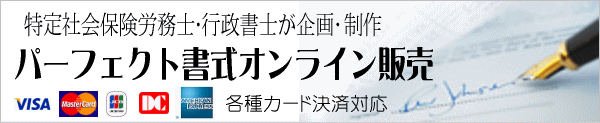
Page Top
【 関連サイト 】
この改行は必要→